相続した田舎の土地を有効活用できずに悩む人は少なくありません。遠隔地にある土地は、往復だけで1日を要してしまう場合もあるため、管理が次第に負担となり、結局は放置されてしまうことも多いのです。一方で、立地条件が良ければ買い手も付きやすく、活用方法が考えられます。このように、田舎の土地であっても相続するメリットは十分にありますが、立地が悪い場合には注意が必要となります。
こちらでは「農地を相続放棄する際の注意点」や「農地処分の基礎知識」をご紹介します。
農地を相続放棄する際の注意点
◇農地のみを限定して相続放棄することはできない
相続放棄とは、相続財産全体に関する権利義務を放棄することを意味します。つまり、積極財産(プラスの財産)か消極財産(マイナスの財産)かを問わず、すべての相続財産について相続の権利を手放すことになるのです。
したがって、都合のよい財産のみを選んで相続し、不要な農地だけを相続放棄することはできません。また、相続放棄はできても、相続で得た農地の所有権を後から放棄することはできません。民法では不動産の所有権放棄を認めていないためです。
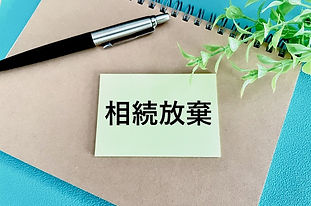
◇相続放棄後も農地の管理義務は残る
農地を相続放棄しても、新しい相続人が相続財産の管理を開始できるまでは、相続放棄した人に「管理義務」が課されます。「管理義務」とは、自らの財産と同様の注意をもって、相続財産の管理を行わなければならない義務のことです。具体的には、以下のような行為が求められます。
-
農地の適切な維持管理
-
小作人への賃料請求
-
小作人の入れ替えなど
このように、相続放棄後も一定期間は農地の管理を怠ることができません。仮に管理を怠れば、損害賠償責任を問われる可能性があります。
◇相続放棄をした場合の農地の所有権に注意
相続放棄をした場合、相続をする権利は、相続人の順位に従い移動します。
具体的には、
-
後順位の相続権を持つ人が相続をすれば、農地の所有権者はその人になる
-
相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなり、相続財産管理人による相続財産の管理清算として競売にかけられた場合には、農地を落札した人が所有権者となる
-
換価や売却ができずに国庫に帰属した場合には、国が農地の所有権者となる
相続放棄をしたにもかかわらず、亡くなった被相続人名義の農地の名義変更を行うと、無条件に相続をしたものとみなされてしまいますので注意が必要です。
農地を処分する前に知ろう!農地処分の基礎知識
農地を手放したい場合はどのような方法があるのでしょうか。日本の食料自給率は諸外国に比べて低く、農業離れが深刻です。そのため、食料供給源としての農地は簡単には用途変更や売却ができず、宅地とは異なる扱いになっています。
農地を処分したいとお考えの際は、まずは農地と宅地の違いや農地転用ができないケースなどを知っておきましょう。
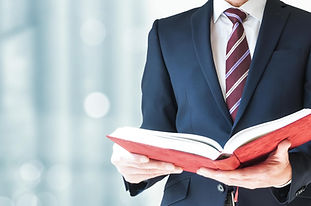
◇「宅地」と「農地」の違い
そもそも「宅地」と「農地」には大きな違いがあります。その主な違いは、地目の定義と固定資産税の評価額の違いです。地目の違いとは、宅地は「建物の敷地およびその維持や効用を果たすために必要な土地」と定義されています。一方、農地は「農耕地で用水を利用して耕作する田」または「用水を利用しないで耕作する畑」と定義されています。
また、固定資産税の評価額にも違いがあります。固定資産税は、土地の評価額に税率をかけて算出されますが、一般的に農地の評価額は宅地に比べて低く設定されています。そのため、同じ広さの土地でも、農地の方が宅地よりも固定資産税額が低くなる傾向にあります。
このように、宅地と農地では、土地の用途と課税の面で大きな違いがあることがわかります。
◇売却方法の違い
宅地と農地では、土地の用途が異なるため、税負担のみならず、売却方法にも違いがあります。農地の場合、売却には農地法による制限があり、以下の2つの方法しか認められていません。
-
農地のままで農家に売却する
-
農地から用途変更を行ったうえで、非農家に売却する
どちらの売却方法を選択する場合でも、農業委員会の許可を得ることが義務付けられています。許可には一定の条件を満たす必要があるため、相続により農地を取得した場合でも、農業委員会の許可が下りないと売却ができない可能性があります。
◇農地を宅地として販売することはできない
前述のとおり、農地の売却は農地法により制限されており、農地のまま農家に売却するか、農地から用途変更をして非農家に売却するかの2通りしか認められていません。つまり、用途変更をしないままでは、農地を宅地として販売することはできないのです。農地の用途を変更し、宅地などの農地以外のものにすることを「農地転用」と呼びます。農地転用を行うには、立地基準と一般基準(土地利用目的や周辺環境への影響など)に基づき、農業委員会の許可を得る必要があります。
農地を宅地に転用すれば購入希望者がつきやすくなるメリットがありますが、一方で相続税の納税猶予の特例を受けられなくなるデメリットもあります。納税猶予の特例とは、高額になりがちな農地の相続税を実質的に免除する制度です。
したがって、農地転用をするかどうかは、宅地への転用によるメリットと納税猶予の特例を失うデメリットをよく検討し、判断する必要があります。農地の売却を検討する際は、このような農地転用に関わる事項を十分に理解しておくことが重要です。
◇農地転用ができない場合もある
農地の転用には、農業委員会の許可が必要です。その許可の可否は、「立地基準」と「一般基準」に基づいて決定されます。
立地基準とは、農地の優良性や周辺の土地利用状況などから、転用する農地を農業上の利用への支障が少ない農地に誘導することを目的とした基準です。許可が最も厳しいのが「農用地区域内農地」で、原則不許可です。次いで「甲種農地」「第1種農地」と続き、「第2種農地」になると一定の条件で許可される場合があります。「第3種農地」は市街地化が進んでいる農地で、原則許可となります。
一方の一般基準は、次の3点を満たす必要があります。
-
転用後の利用目的が確実であること
-
周辺農地の営農条件に支障がないこと
-
一時的転用の場合、利用後に農地として復旧できること
このように、立地基準と一般基準のクリアが難しい場合は、農地の転用が許可されない可能性があります。農地所有者は、このような農地転用の難しさを十分理解したうえで、対応を検討する必要があります。
相続放棄も含め農地処分のことなら株式会社ゴダイリキへ
田舎の農地は、先祖から代々受け継がれてきたものである場合や、草刈りなどの管理が義務付けられていて放置できない、メリットがなくとも相続せざるを得ないといったケースもあります。しかし、負の財産はいずれ子供や孫の重荷となってしまう可能性があります。そのため、相続するべきか相続放棄するべきかといった判断には長期的な視点を持つことが重要となります。
田舎の農地処分でお悩みの際は、株式会社ゴダイリキへご相談ください。株式会社ゴダイリキでは、農地や空き家など売却が困難な不動産、いわゆる「負動産」の買取りに全国で対応しています。負動産の処分や売却でお悩みのお客様には、専任アドバイザーが真摯に寄り添い、一から丁寧にサポートさせていただきます。
長年手放せずにいた農地や実家の空き家など、活用の道がなく頭を悩ませている負動産がございましたら、お気軽にご相談ください。お客様に最適な方法をご提案いたします。
農地や畑の処分・放棄でお困りの方に役立つコラム
土地や山林、ボロ物件といった「負動産」の処分方法でお困りなら株式会社 ゴダイリキへご相談ください
株式会社ゴダイリキでは、土地や山林、ボロ物件といった「負動産」の買取を行っています。地理的なアクセスの悪さや管理の不行き届きなど、買い手が見つかりにくい土地や売れない別荘も有償ではございますが、買取しています。
無料相談を実施しており、専任アドバイザーがわかりやすい言葉で丁寧に説明いたします。また、使われていない土地や別荘の処分を急ぎたい方にも迅速に対応しいたします。
土地や山林、ボロ物件といった「負動産」の処分にお悩みの際は、ぜひご連絡ください。手放すのが困難な不動産の処分方法に悩む方を、積極的にサポートいたします。
田舎の農地処分をお考えなら株式会社ゴダイリキ
[社名]
株式会社 ゴダイリキ
[本社住所(東京オフィス)]
〒112-0013 東京都文京区音羽1-2-8 江戸商事ビル301
[TEL]
[FAX]
050-3451-0775
[URL]
[受付時間]
平日10:00~19:00
[定休日]
土・日・祝日
[業務内容]
リゾート物件の処分(休眠分譲地や山林・原野など市場で売却困難な土地、リゾート会員権を有償で引き取り)





